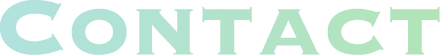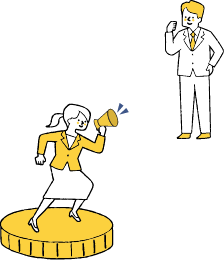よくある質問
- ホーム
- よくある質問
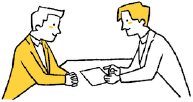
FPチアーズ株式会社
に関するご質問
相談していい内容はどんなものですか?
確定拠出年金、iDeCo、NISA、相続対策・ 遺言書作成サポート、老後の資産形成など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。
「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
相談はどのような方法で行いますか?
訪問・来訪・電話・オンラインなどご希望に合わせて対応いたします。
まずはお問い合わせください。
相談に費用はかかりますか?
相談料は11,000円(税込)となります。
(初めてのお客様:90分・2回目以降のお客様:60分)
【LINE友だち追加で、個別相談無料キャンペーン実施中!】
営業を強く勧められないか心配です。
相談において、特定の金融商品の勧誘はありません。お客様からご希望があった場合に、最適なプランをご提案しています。
営業時間はいつですか?
平日9:00〜17:00となります。
相談時に持参するものはありますか?
相談内容に合わせて事前に告知させていただきます。
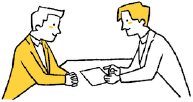
確定拠出年金に関するご質問
導入の条件はありますか?
厚生年金の適用事業所であれば1名の加入から導入可能です。
社長お1人からでも導入できますのでお気軽にお問合せください!
導入にあたって、どのくらいの手間やコストがかかりますか?
加入条件により異なりますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
具体的な税制メリットのシミュレーションは可能ですか?
もちろんです!
無料でシミュレーションすることが可能ですのでお気軽にお問合せください!
他の支援会社とどう違いますか?
企業、個人それぞれに合わせた提案が可能です。
導入から運用・従業員向けのサポート・管理までワンストップでサポートします。
有期契約社員や、パート・アルバイトはどうなりますか?
厚生年金被保険者であれば、加入する事は可能です。
途中で辞めることもできますか?
原則、掛金の積み立てを停止することはできません。
ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、規約に定めることで掛金の積み立てを停止できます。
掛金を停止すると、加入者ではなく「運用指図者」となって、今まで積み立てた額の運用を続けることとなります。
希望する従業員のみ加入することはできますか?
所定の手当を支給する制度を設け、現金で受け取るか、確定拠出年金の掛金として積み立てるかを選べる選択制とすることで、希望者のみの加入が可能となります。希望しない従業員は現金で給与に併せて受け取ります。
年金資産の引き出しはできますか?
原則、途中引き出し・解約は認められていません。
年金資産は「一定の年齢(60 歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
加入者本人がお亡くなりになった場合は遺族が死亡一時金として、また傷病により一定以上の障害になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6か月)を経過した場合は障害給付金として受給が出来ます。
自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください。
確定拠出年金法では、自己破産したとしても差押することは禁止されています。
確定拠出年金法第32 条では、
「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、
会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。
中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。
企業型確定拠出年金を受け取るまでに退職(転職)したらどうなるのでしょうか?
転職先に企業型確定拠出年金があれば、そのまま移動する事が可能です。 転職先に制度がない場合や、自営業・公務員・専業主婦(夫)になる場合は、個人型(iDeCo)に移行するか拠出を停止するかを選択する事が可能です。
また、退職後の下記の場合もiDeCoへの移換が可能です。
- ・自営業を営む場合
- ・仕事をしない場合
- ・専業主婦になる場合
- ・公務員になる場合
※退職から6か月以内に移換手続きが必要です。
期限を過ぎると、年金資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます。
自動移換された場合、「管理手数料が発生する」「資産の運用ができない」「税制優遇が受けられない」等のデメリットが発生します。
※脱退一時金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。